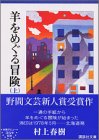こんなエントリがありまして、まあ思わずのってしまったってことで。
なんでも読み返したくなるっていうことは、やっぱり手元にある漫画じゃないと話になりません。という縛りがあることにしましょう。あと、完結済みっていうのも一応条件として。
ちなみに、うちの漫画棚はこんな感じ。もともと持っていたもの半分近くはいまだに実家にあったり自炊しちゃったりなので、これでもそこそこ絞られている、はず。
単行本・文庫本サイズの漫画は全部前後2列になってるわけですが、さすがにそろそろあふれそう。どうしようかなあ。
それはさておき。
AKIRA
 |
AKIRA(1) (KCデラックス 11) 大友 克洋 講談社 1984-09-14 by G-Tools |
説明要らずの定番、だと思う。
読み返したくなるというか、少なくとも2-3回は読まないと筋を把握できない気もする。まあ、それ以上に読み返しているけれど。
寄生獣
 |
寄生獣(完全版)(1) (アフタヌーンKCDX (1664)) 岩明 均 講談社 2003-01-21 by G-Tools |
これも定番ですな。
高校の部室においてあったのを何度も読んだのが懐かしい。その後、完全版が出てから全部そろえたわけですが。
アタゴオル物語
 |
アタゴオル (1) (MF文庫) ますむら ひろし メディアファクトリー 1999-11 by G-Tools |
直近では続々編の「アタゴオルは猫の森」だけれど、やっぱり初期のシリーズが一番新鮮で面白い。まあ、当然全シリーズ持ってますけれど。
七色いんこ
 |
七色いんこ (1) (秋田文庫―The best story by Osamu Tezuka) 手塚 治虫 秋田書店 1997-03 by G-Tools |
手塚作品の中では一番好きかな(あー、鳥人大系も名作だ!)。演劇がテーマの泥棒の話。って書くとなんのことやらですが、本当にそういう話。
なつのロケット
 |
なつのロケット (Jets comics) あさり よしとお 白泉社 2001-07 by G-Tools |
小学生が夏休みの宿題に人工衛星を作る話。もう、読むたびに最後の1コマで何度も泣いたよ。宇宙好きにはたまらんよ。
番外
冒頭の条件をはずすと、今一番のはやりは当然これ。
 |
ONE PIECE 1 (ジャンプ・コミックス) 尾田 栄一郎 集英社 1997-12-24 by G-Tools |
ええ、もう、今や毎回発売日に買い続けてますからね。(上の本棚写真の一番下の段は全部これ。で、あふれてきたので下から2段目にも・・・)
まあ、そんな感じですかね、と。
で、書いていて思ったけれど、これらって自分が好きな漫画であると同時にみんなに読んで欲しい漫画になりますね。あーまた全部読みたくなってきた。