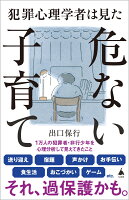学校関係からちょっとオススメされまして、そしてちょうど読む本ないタイミングだったのでさくっと。
自分的には子育て後半戦には突入していると思っているんですが(あと10年も経たないうちにみんなが独立する、はず)、そんなわけでちょっと今さら?かなと思いつつページをめくってみたけれど、いろいろうなずけること盛りだくさんで今からでも参考になりそうなことたくさんあったわ。
というか、基本的に犯罪を犯した子の話からスタートするので、そしてちょうどまさにそういう時期(思春期から青年期)にさしかかっているっていうところなので、その意味ではドンピシャだった。
自分は大丈夫、うちの家族は大丈夫、と思い込まずに、できるだけ客観的に見られたらいいんですけどね、難しいですよね。
なんでもバランス大事なので、極端でなければ大丈夫なんですけれど、とはいえ、程度問題ではあるけれどやっぱり偏ってはいるよねえ>自分、と省みながら。
たまにはこういう本もいいですね。成功体験の本はとくに読むモチベーションあがらないですが、こういうのは逆に参考になりそうで。というか、子育て関係の本まじめ読んだの、初めて?超ひさしぶり?文章も読みやすくて通勤時間だけで1週間もかからなかったです。
ちなみに、冒頭を読みながら思ったことは「あ、これNewtonで読んだわ」でした。たまにNewtonで心理学系の特集が組まれることがあるんですが、そういうところで結構触れられてる話もあって、心理学は科学ですからね、と。